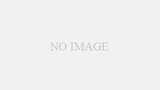夜中に、家の中で駆けずり回り、ソファーに激突してキャンと悲鳴。
以後、右後ろ足を痛がり、挙上して地面に着かないとのこと。
電話でお願いしたこと
お電話で、おおよその状況はわかりました。
原因がかなりはっきりとした、「事故・怪我」と思われます。
お願いしたことは、以下となります。
・時間を正確にメモしてもらうこと
・安静に努めること
・今の状態を動画に残してもらうこと
・頻繁に様子を確認した上でお越し頂くこと
・目撃した人、あるいは一番詳しい状況把握ができている方を同伴してもらうこと
以上となります。
もちろん、最近やった検査結果や飲んでいる薬・サプリがあれば持参して頂くようにお願いしておきました。
これは、どの症例でもそうですね。
抜粋して主旨をご説明します。
動画を撮影する重要性
これは、あるあるなのですが、「動物病院に到着した途端に元気になってしまい、全ての症状がなくなった」というのがあります。
もちろん、飼い主さんがウソをついているとは思っておらず、興奮したりして交感神経が優位になるとこういった現象はよく起きます。
時間経過で良化してしまったというのも良くあります。
本能的に第三者に隠すということもあります。
症状は、「もっとも悪いときに観察する」と一番ヒントが多いことがあるため、動画での情報は非常に有益です。
どこを撮影して欲しいか・・・については、各症例ごとに違いますので、逐一お願いする内容は変ります。
頻繁に様子を見て頂く
たまーに、「外傷性ショック」を起す子がいます。
外傷を契機として、突発的に出現する持続的な末梢循環不全の状態を「外傷性ショック」と呼ぶのですが、死に至ることがあるため、注意が必要です。
ソファーにぶつかったくらいでは起きず、交通事故などや広範囲の外傷などで起きやすいのは事実ですが、起きる可能性はあります。
ちなみに、筆者は犬に噛まれて、数分後にこれになったことがあります。
そのため、どんな外傷でも起きうるとして、注意喚起しています。
時間の計測と、詳しい人を同伴
これは説明するまでもないかも知れませんが、より正確な情報を得るためです。
動物病院に連れてきた人が「現場見てないからわからない」「普段の様子からしてわからない」という状況では、どうしても正確な診断には到達しづらくなります。
診察において、もっとも重要なものとして位置づけしているのは「問診」です。
そのため、なるべく詳細に問診に答えられる人がお越し頂くのが最良となります。
直接見たか?は最も重要な確認ポイントです。
足を上げているから、足をぶつけたと思い込んで喋っていることは多いですが、実際に見ていないのであれば、広く損傷箇所を疑うべきです。
検査の重要性
現場で働いている人は、同意してくれると思いますが、問診で70~80%くらいは、「あたり」がつきます。
病名の特定には至らないまでも、「アレか、コレか、あるいはアレだな」みたいなのがおおよそわかることが多いのです。
そのため、血液検査やレントゲン検査なども非常に大切ですが、最も重要なものは問診となります。
問診で病気を予想して、血液検査やレントゲン検査、エコーで「確認・確定していく」というのが近いかもしれません。
とはいえ、問診でさっぱりわからないこともありますし、予想と違った結果になることもたくさんあるため、やはり「検査」は非常に重要となります。
検査のご提案
さて、今回のワンコさんは、来院したら走り回っておりました・・・・・
あるあるです。
見てわかる触ってわかる範囲での検査を実施します。
明らかな外傷なし、出血なし、意識レベル問題なし、神経症状無し、触診上は疼痛反応なし、関節可動域正常、負重にも耐えられる、歩様正常
端的に問題なさそうです。
おそらくは、一時的に痛めただけの「打撲・捻挫」の類いでしょう。
しかし、確認としての検査で、レントゲン検査を強くお勧め、血液検査は希望があれば、、、というレベル感で勧めました。
レントゲン検査
明らかな骨折・脱臼や、有意な腫脹がないかどうかの確認のため、こういった場合は強く勧めています。
問題がないことの確認というのも大事ですし、「実際は折れていた」ということも経験上あるからです。
必須という認識です。
撮影部位については要相談ですね。
これは、必ずしも対象となる足とは限りません。
*頭や腰なども検討対象ですが、少なくとも健常な方とワンセットで撮影が基本です。
血液検査
一応、ご提案はしますが、正直あまり意義は高くありません。
たまたま事故が重なっただけで、実は何らかの基礎疾患があって、足の挙上という症状が見られる・・・という可能性もなくはないです。
*実は、ぶつかったときに他の部位が損傷していたなんてケースは非常に、非常に多いです。
その際には、脳・神経・肝臓・腎臓・心臓・栄養失調・脱水・貧血・代謝異常など、さまざまな要因でふらつきなどが出ます。
とはいえ、そういった状態であれば、そうそう元気にはしていないことが多いのも事実です。
*てんかんなどの神経疾患や、不整脈、心臓発作などは別として
CPK、GOT(ALT)、CRP、WBCなどを評価することも大切ではありますが、絶対にした方が良いという必須検査というよりは少し重要性は落ちます。
*頭部外傷は別です。
*個人の見解です。
なので、飼い主さんにご提案する際には、その優先度?必須度?もあわせてご説明します。
治療
結論として、今回は飼い主さんのご要望で、検査は未実施となりました。
これは決して悪いことではありません。
検査をしないリスク、コスト(金銭・身体的負担、待ち時間など様々な)と、実施メリットを考えた上での決断ですので、善し悪しはありません。
内容についてよく説明をし、十分理解した上で、飼い主が自らの意志に基づいて、検査や治療の方針に合意する(あるいは拒否する)インフォームド・コンセントが重要です。
と、いうことで、軽めの消炎鎮痛剤を投与し、本日は絶対安静を指示してお返しとなりました。
ご説明
消炎鎮痛剤を投与した際は、あわせてセットで絶対安静のため、そこは注意いただくようにお伝えしました。
また、こういった事故の場合、「時間が経ってから症状が出る」ことが往々にしてあるため、2~3日は要観察をお伝えしております。
*うっすらとヒビが入り、時間経過でポッキリ折れて骨折などがあります。
*内臓のダメージもジワジワと顕在化することがあります。
消炎鎮痛剤を投与して、数日で完治しない場合も、追加でレントゲン・超音波検査・CTやMRI、血液検査などの追加検査が必要となることがあります。
いずれにせよ、翌日主治医を受診するように必ずお伝えしています。
夜間にペットの体調が悪くなったら
動物病院の受診をお勧めします
港区(東京23区)
所在地
〒106-0041 東京都港区麻布台3-3-14 TAS 麻布台レジデンス1階
営業時間
20:00~翌5:00
お電話
050-5491-7200 *必ずお電話でご予約の上お越し下さい。
電車でお越しの場合
東京メトロ日比谷線「六本木駅」から徒歩5分
東京メトロ南北線「麻布十番駅」から徒歩5分
都営大江戸線「麻布十番駅」から徒歩5分
車でお越しの場合
首都高速都心環状線「一ノ橋JCT」近く
※駐車場はございませんので、近隣のコインパーキングをご利用ください
執筆 K-VET