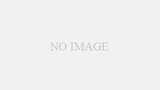ゼリー状の粘膜とともに、便に血が混じるワンコが来院しました。
前日には下痢をしていたとのことでした。
電話でお願いしたこと
お電話では、心当たりがないとのことでした。
お願いしたことは、以下となります。
・あれば、、、便を持ってきてもらう、あるいは、写真を撮ってきてもらう
これだけです。
毎度のことながら、最近やった検査結果や飲んでいる薬・サプリがあれば持参して頂くようにお願いしておきました。
どこからの出血なのかを知る
一言に便に血が混じるといっても、さまざまです。
一番大切なのは、出血の場所です。
これは、上部消化管からの出血なのか、下部消化管からの出血なのかということです。
厳密には色だけではないのですが、ざっくりと「出血の色」で判断します。
赤ならば鮮血として、下部消化管と推測します。
黒・褐色ならば、上部消化管と推測します。
一概には言えませんが、上部消化管からの出血であれば重篤な疾患であることが多いため、緊張が走ります。
幸いにして、今回はゼリー状の粘膜に、赤い鮮血が付着した状態でした。
量もそれほど多くなく、出血は軽微と思われました。
便に粘膜が付着しているか
テカテカと光るゼリー状のものがあれば、腸粘膜か腸粘液と呼ばれるものとなります。
これ自体がイコール病気というわけではなく、正常でも腸の粘液は出ます。
しかし、腸に炎症が起きた場合に粘液は多く分泌し、また、腸の内側は粘膜で保護されているため、これが何らかの原因(下痢・便秘や様々な要因)で剥がれ落ちて便とともに排出されることがあります。
腸の内側表面を保護している粘膜が剥がれ落ちると、出血があることがありますので、血便を起こしている場合は、高確率で、この粘膜も確認できることがあります。
正常でもでることがあるため、必ずしも重要な所見ではありませんが、腸炎と出血を疑う要因とはなるため、確認はしています。
便の性状
個人的には、これを一番重要視していますが、便の性状です。
具体的には、下痢をしているか、どのくらいの水分含有量で、どの程度の回数か、ということです。
また、臭い(酸味臭や腐敗臭など)、色(緑・黄色・白など)も併せて重要です。
細かい鑑別は別の機会に譲りたいと思いますが、診断に直結することもあるため非常に重要で、かつ、脱水などの状態の評価・予測にもつながるため必須の観察ポイントになります。
便検査
持参していただいた便での検査は実はあまり便検査には有益でないことが多いです。
せっかく便を持ってきたのに、パッと見ただけで、その便で検査をしてくれない・・・そんな経験はないですか?
新鮮な便でないと、「菌」は観察できないので、直接は使用されないことが多いのです。
もちろん、寄生虫の検査はできるのですが、実際には寄生虫に感染しているケースは室内飼育の成犬・成猫では稀です。
そのため、便検査をあまり実施しない動物病院もいるかもしれません。
これが良いか悪いかは何とも言えません。
結果論として、何も出なければ、「無駄な出費・無駄な検査」と言われてしまうこともあり、実際に寄生虫でないケースが多いため、ヒット率は低いのは事実です。
そのため、「確率的に低いことは実施しない」というのも一つの正解だと思います。
私は、直接塗抹という少量の便、簡易な検査だけ必ず実施するようにしています。
これで、同一形態の有意な菌の増殖と、虫卵(便が少量のため、精度は低くなりますが)の検出、性状(未消化物や異物など)などはわかりますので。
検査のご提案
さて、今回のワンコさんは、上記の通り便検査は必須でご提案し、実施。
追加の検査で、レントゲン検査、血液検査をお勧めました。
レントゲン検査
今回は鮮血のため、下部消化管からの出血を疑いました。
したがって、腹部のレントゲンを撮影しました。
出血の原因となる疾患はいくつかあるものの、特定できる可能性は決して高くありません。
しかしながら、特定できる場合も当然あります。
ここは、ヒット率は低く、手探りながらも実施する価値はありますので、レントゲン検査を実施します。
何もなければ、「特に大きな問題がない」という素晴らしい結果が得られます。
原因がわからないことが決して悪いことではなく、「明確な悪い原因がない」ということはよいことでもあるのです。
血液検査
貧血、止血異常、脱水、感染・炎症、各種内臓疾患、電解質バランスなど、評価する上で重要なことが多々あります。
そのため、筆者の中では非常に有意義な検査なのですが・・・残念ながら血便の原因特定にはむずびつかないことが多いです。
今回は、お年の割には、非常にきれいな健常値が出ました。
よかったです。
診断
ということで、問診・視診・聴診・触診と便検査、レントゲン検査、血液検査を実施いたしました。
結論としては、「わからず」となりました。
これは事前に飼い主さんにご説明済みであり、想定通りの結果となります。
嘔吐・下痢も不明なことが多いですが、血便もまた、「原因不明」というのが非常に多いです。
あれやこれやと検査を実施して、結果、何の異常も出ないというのが一般的です。
ただ、この「何の異常も出ない」というのが重要だと考えています。
消去法的に、一過性の単純性大腸炎である可能性が高まり、対症療法で治癒する可能性が高くなります。
腸粘膜の再生能力は高く、数日で再生するといわれています。
そのため、対症療法によって数日~一週間、あるいは10日ほどで良化することが期待できます。
しっかりと治療をして、それでも良化しない場合は、超音波検査やバリウムのような造影剤の検査、CT、内視鏡、最悪は試験開腹といった追加検査によって精査することになります。
筆者は、下痢や嘔吐・血便などは来院頻度が多く、ほとんどが上記に該当するため、夜間救急においてはこういった対応をすることが多いです。
重症度が高い、緊急性があるなどの場合は超音波検査の追加をすることもありますが、時間的ゆとりがある場合は、翌日の主治医での精査をお願いすることが多くなっています。
治療とご説明
原因は不明のため、対症療法を実施して終了となります。
消炎止血剤・下痢止め・補液(脱水の予防として)を実施しました。
ピタッと出血や下痢が止まるほど著効するわけではないことと、基本は数日間の治療でワンセットという概念でいていただきたいことをご説明し、多少は状態に波がある(良くなったり悪化したり)ものの、次第に良化する可能性が高いことをご説明しました。
逆に、しっかりと対症療法を実施していても良化しきらない場合は追加での精査が必要であることを忘れないように、とも説明。
食事については様々な意見があり、獣医師によって指示が異なるかと思います。
夜間救急において、筆者はこういったケースでは主治医を受診するまでは絶食絶水をお願いしています。
夜間にペットの体調が悪くなったら
動物病院の受診をお勧めします
港区(東京23区)
所在地
〒106-0041 東京都港区麻布台3-3-14 TAS 麻布台レジデンス1階
営業時間
20:00~翌5:00
お電話
050-5491-7200 *必ずお電話でご予約の上お越し下さい。
電車でお越しの場合
東京メトロ日比谷線「六本木駅」から徒歩5分
東京メトロ南北線「麻布十番駅」から徒歩5分
都営大江戸線「麻布十番駅」から徒歩5分
車でお越しの場合
首都高速都心環状線「一ノ橋JCT」近く
※駐車場はございませんので、近隣のコインパーキングをご利用ください
執筆 K-VET