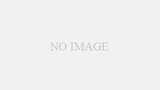ペット用のおもちゃとして開発・販売されているおもちゃでも、トラブルはおきます。
メーカーの製造物責任の問題も正直あるかと思いますが、ワンコやニャンコも、種類や大きさ、性格など様々ですので、、、
正規の使用方法や適用基準から外れることもあるでしょう。
なにより、予想の上を行くのが動物です!
ということで、シリコン製?と思われる骨型おもちゃをガジガジして、一定の破片に砕かれているものの、飲み込んでしまった犬が来院しました。
犬の誤食で飼い主さんに聞くべきこと
さて、毎度のことながら、問診からスタートです。
この問診が最も重要となります。
じっくりとお話しを伺いますが、誤食については胃の中にある時間にタイムリミットがありますので、そこは意識しておきます。
犬が食べるところを実際に見たのか・・・
必ず聞かなければいけないことは、
『実際に、食べた現場を直接見たかどうか』
となります。
こういった誤食のトラブルの場合は、最も重要な確認ポイントです。
レントゲンで映るものであれば良いのですが、そうでない場合、
『そもそも本当に食べたのか』
というのは、とても大切なことです。
吐かせたは良いけど、誤食したものが確認できない、あるいは、出て来たけど、全量かどうかはわからない・・・ということがあるためです。
全身麻酔をかけて、内視鏡ということであれば、胃の中をある程度は確認できますが、、、ある程度になってしまうこともあります。
また、「すでに腸に流れてしまった」という可能性も考えると、もはや確認不能となります。
なお、残された破片などがあれば、逆算して、食べた可能性が高い量が想像できる場合もありますが、今回は、すでにボロボロのおもちゃだったため、不明でした。
犬の誤食で他に飼い主さんに聞くべきこと
上述の通り、実際に食べた現場を目撃したかどうかは、非常に重要です。
他にも必ず確認すべきことはいくつかあります。
・いつ食べたか(あるいは、いつからいつの間に食べた可能性があるか)
・他にも何か食べた可能性はあるか
・いままでもこういったことがあるか(あるならば、その際の処置・結果も)
・他に動物を飼っていて、そっちが実は・・・というオチがないか
いくつかある可能性を考えながら、『飼い主さんの推測・思い込み』ではなく、『事実』を聞いていきます。
意外と「こうに違いない!」という思い込みで断定的にお話しする方が多いので、そこを細かく確認していきます。
飼い主さんの仰ることを全て鵜呑みにするのではなく、「あらゆる可能性を排除しない」ということが大事になります。
関連する既往歴
ここから、検査を実施して、吐かせる処置を検討していきます。
実際には、吐かせない場合もありますし、内視鏡や開腹手術、経過観察などの色々なフローを検討していくことになりますが、今回は吐かせる前提でお話をします。
確認すべき既往歴は特に以下です。
・循環器疾患
・呼吸器疾患
・消化器疾患
・アレルギー
・癲癇(てんかん)などのけいれん発作を含む神経疾患
・直近で手術をしていないかどうか
・血液検査上の異常を認めたかどうか
・腫瘍
などになります。
これは、一つでも該当していたら、吐かせられないというわけではありません。
事前にリスク評価が必要であり、吐かせるメリットとデメリット・リスクを推し量るということになります。
誤食で催吐処置を行なう前に実施する検査
必須で実施させて頂いているのは、レントゲン検査となります。
既往歴によっては、血液検査も実施となります。
一般身体検査と、バイタル評価を済ませたら、レントゲン検査を実施します。
レントゲン検査を実施する目的としては、
①胃の容積を知る
②誤食した異物を確認する(見えないことがわかっている場合は当然期待しない)
③他に変なものを食べていないかどうか(意外とある)
④他に催吐が禁忌・困難となるような疾患がないかの確認
⑤食道・胸部の評価
よく、「レントゲンに映らないのに、検査は必要ですか?」と聞かれます。
当然ですが、必要です!!
検査を提案するときに、『できれば実施が好ましい』と、『絶対に必要です。未実施では処置ができません』など、何パターンかありますが、この場合は必須と考えています。
①~⑤にあるように、レントゲン検査を実施する理由は「誤食した異物を見る」ためだけではないからです。
①~⑤について、理由や詳細を述べていきたいところですが、今回は割愛します。
催吐処置はリスクがある
一通り、問診、身体検査、レントゲン検査を実施し、状況が把握できたため、催吐処置を実施します。
本来であれば、催吐処置を実施すべきかどうか、他の選択肢はないかのお話しもしたいのですが、別の機会に致します。
ここで、催吐処置のリスクについて飼い主さんに説明、処置の同意を取ります。
①誤嚥性肺炎が起きる可能性がある
②逆流性の食道炎・胃炎が起きる可能性がある
③薬剤の効果により、けいれんが誘発する可能性や肝障害・腎障害の可能性がある。
また、鎮静効果が発現することがある。
これらをご説明します。
使用する薬剤によって、ややリスクは変りますが、おおよそ上記の説明をすることが多いです。
多くの飼い主さんが、「催吐処置はリスクがほぼない」と思っているようで、説明をすると驚かれることが多いです。
最後に、、、吐かないことがあります。
これは、目的の異物を吐かないということもそうですが、そもそも嘔吐すら起こらないということがあります。
感覚的に、犬では80%、猫では25%くらいの催吐成功率です。
犬が誤食した異物を、催吐させる
ここから催吐処置を実施することになります。
①留置針を設置(ルート確保)
②嘔吐を引き起す薬剤を投与
これらを実施致します。
薬剤については何種類かあるのですが、段階的な使用を考えて選択します。
ここは獣医師によってわかれるところでしょう。
今回は、上手く吐いてくれました!!!
人間の小指の第1関節くらいの大きめの粒状にかみ砕かれたシリコンの破片が2つ出て来ました。
犬種にもよりますが、種やビー玉程度で十分に閉塞します。
今回も、小型犬であることを考えると、詰まっていたとしてもおかしくはなかったので、良かったです。
催吐処置後の治療とご説明
吐かせて、無事に異物を回収できたので、おしまい!といきたいのですが、
①胃酸分泌抑制剤(胃粘膜保護剤)
②吐き気止め(制吐剤)
を今回は処置致しました。
場合によっては、補液をすることもあるのですが、今回は見送りました。
催吐に使った薬剤によって異なりますが、その後に吐き気が継続するものや、
すぐに吐き気が消失するものなどあります。
それによって、やや対応が変るのですが、たいていは上記の処置を実施します。
ご自宅に戻って、しばらく安静に努めた後いつも通りにして頂いて大丈夫です。
ただ、冒頭にもう少し触れましたが、残存リスクはあります。
今回は複数回吐かせて、もう何も出てこない状態まで確認しましたが、それでも胃の中にまだ欠片がある可能性は否定できません。
誤食から催吐まで、経過時間が短かったため、腸に流れた可能性は低いと思いますが、これもゼロではありません。
数日は、うんちをほぐして、異物がないかどうかを確認するとともに、閉塞症状がでないかどうかを観察して欲しいとお伝えしました。
そして、飼い主さんの管理上の問題でもあるため、諸注意を促して治療完了です。
(飼い主さんの適正な飼育管理の指導も獣医師の仕事なのです)
*長々と書いたようですが、実際にはだいぶ説明を端折っています。
これが全てではありませんので、読み物として見て頂ければと思います。
なお、翌日に、主治医にはご報告をお願いしました。
夜間にペットの体調が悪くなったら
動物病院の受診をお勧めします
港区(東京23区)
所在地
〒106-0041 東京都港区麻布台3-3-14 TAS 麻布台レジデンス1階
営業時間
20:00~翌5:00
お電話
050-5491-7200 *必ずお電話でご予約の上お越し下さい。
電車でお越しの場合
東京メトロ日比谷線「六本木駅」から徒歩5分
東京メトロ南北線「麻布十番駅」から徒歩5分
都営大江戸線「麻布十番駅」から徒歩5分
車でお越しの場合
首都高速都心環状線「一ノ橋JCT」近く
※駐車場はございませんので、近隣のコインパーキングをご利用ください
執筆 K-VET